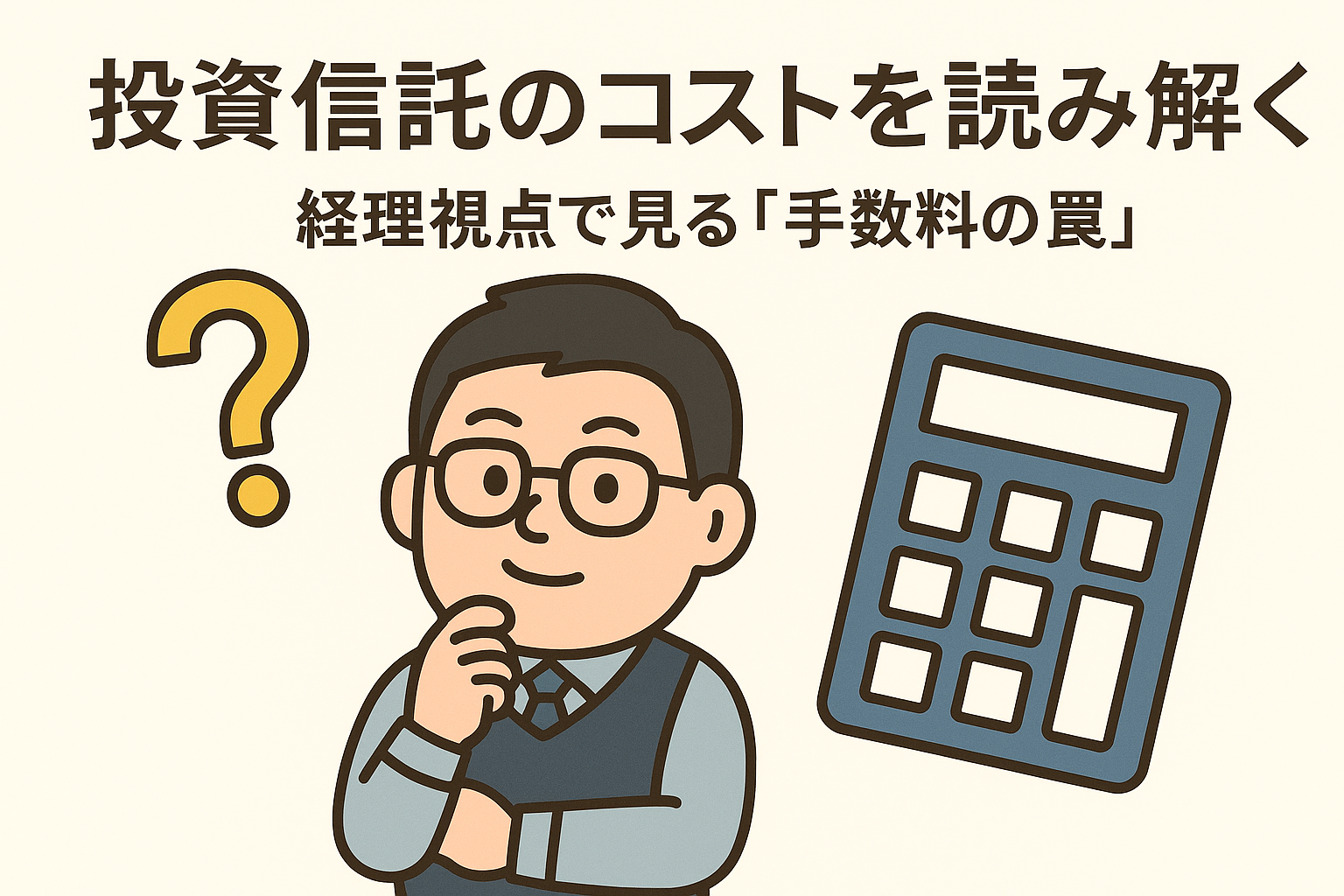経理視点で見る「手数料の罠」|投資信託のコストを読み解く
投資信託を選ぶとき、「なんとなく人気があるから」「S&P500って書いてあるから安心」といった理由で選んでいませんか?
でも、経理職の私から見ると、「コスト構造こそ、投資信託選びで見落とせないポイント」だと実感しています。
実は同じような指数に連動している投資信託でも、手数料(信託報酬)には驚くほど差があるのです。
手数料0.1%と0.5%の差は侮れない
たとえば、信託報酬が「0.1%」と「0.5%」のファンドを比較してみましょう。
一見、0.4%の差なんて小さく感じるかもしれません。しかし長期運用ではこの差が雪だるま式に効いてきます。
仮に100万円を年利5%で20年間運用した場合、手数料の差だけで最終的な受取額に数十万円の差が出ることも珍しくありません。
経理だからこそ見逃せない「コストの内訳」
私は普段から会社の経費や損益を細かく見ていることもあり、投資信託の「隠れコスト」にも敏感です。
具体的には、以下の3点に注目しています。
- 信託報酬:ファンド運用にかかる基本的な手数料。毎年かかる。
- 売買時の手数料:購入・売却時に発生することがある費用。
- 実質コスト:目論見書に記載されていない「その他費用」も含んだ、実際の負担。
この中でも、信託報酬は毎年自動的に引かれるため、長期投資では最重要です。
初心者が陥りやすい“名前だけで選ぶ”落とし穴
たとえば「米国株式インデックスファンド」と書いてあっても、運用会社によって信託報酬は0.1%未満から0.5%以上までさまざまです。
名前が似ていても中身(コスト)が全然違うのが投資信託の世界。
だからこそ、「eMAXIS Slim」シリーズのような超低コストファンドが選ばれているのです。
関連記事:
→ eMAXIS Slimを買ってみた!少額投資のリアル体験記
まとめ|投資こそ“損益計算”が活きる
私たち経理職が普段から使っている「損益思考」は、投資にもそのまま使えます。
目先のリターンだけでなく、「いくら手数料を払っているか」にも注目。そうすることで、本当に“得する投資”を選べるようになるのです。
これから投資を始めようという方は、ぜひ「コスト」という視点も持って、自分にとってのベストなファンドを選んでください。